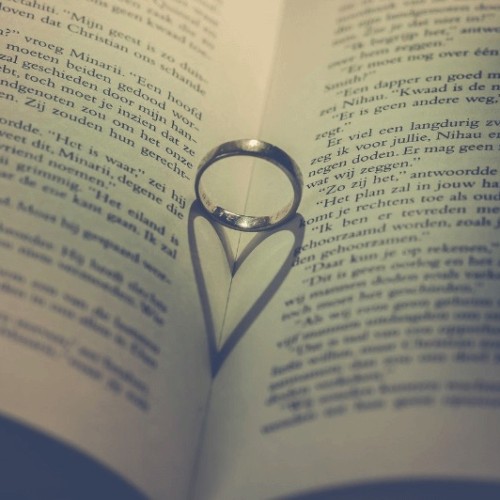30代モテ妻はどうしてる?結婚したら知っておきたい子供の教育ルール

MENU
はじめに
結婚をして幸せいっぱいだけれど、正直子育てには自信がない。
子供がいる友人を見ていても、すごく大変そうに見える。
このように、教育に関して不安を抱えている女性は多いと思います。
子育ては1年という短距離走で終わるものではなく、長距離のマラソンのようなもの。
体力はもちろんのこと、忍耐力も必要になる日々が続きます。
ですが、子育てはチームワークだと思えば、気持ちも軽くなりませんか?
一人だけで抱え込む必要はないと知れば、子育てを前向きに捉えることができるようになっていくはず。
今回の記事では、旦那さんと支え合いながら子育てをしていくために、一緒に共有しておきたい子育ての教育ルールを5つご紹介いたします。
今のうちに知っておくことで、教育に関する 二人の 価値観をすり合わせることができます。
恋愛・結婚・子育てはパートナーと話し合うことで一緒に歩むのが特に健全な姿です。この機会に二人で考えていただけたら幸いです。
旦那と今から共有しておきたい教育ルール5選

一緒に声を出して笑う
子供は母親のお腹にいる時から、外の会話を聞いているそうです。
ですので、夫婦の幸せそうな会話や笑い声が聞こえると、赤ちゃんも嬉しくなります。
また、産まれた後も赤ちゃんは両親の表情を真似ようとするので、たくさん笑顔を見せたり声を出して笑うと、同じようによく笑う明るい子供に育ちます。
夫婦関係においても、笑い合う笑顔の絶えない空気を作るようにすると、仕事や子育てに前向きになれますよね。
叱り役となぐさめ役を分担する
子育てにおいて叱る機会は必ず出てきます。
その時に、両者が責めてしまうと子供は居場所を失った感覚に陥るそうです。
そうなると孤独を感じますし、家にいることがダメなことだと思ってしまいます。
叱るときは、後から片方がフォローを入れるという流れを作っておきましょう。
また、注意する時に感情的に「怒る」ことはなるべく避けてください。
「叱る」というのは根拠と理由を明確にして伝えるということです。
なぜ注意されたのかがわからないと、子供は混乱してしまいます。
習い事は目的を明確にしてから通わせる
子供を習い事に通わせる家庭は多いと思いますが、目的や将来像を見越して通わせている両親はどのくらいいるのでしょうか?
近年増えてきているのが、英語教室です。
小学校3年生から英語科が始まるので、早いうちから習わせておきたい親心はわかるのですが、
「学校のテストで良い点を取ってほしい」のか、「英語を話せるようになってほしい」のかが混同しているパターンが目立ちます。
テストで良い点を取ったり、資格を取得させたい場合なら、文字が書けてかつ言葉を理解する年齢に習わせるのがよく、会話であれば幼児の頃からでも問題ないと思います。
周りのママ友が通わせているから、という理由で習い事をさせると、子供も目標ややりがいを持てません。
月謝も安くありませんので、夫婦、そして子供の3人で話し合いましょう。
言葉遣いに気をつける
子供は親の話し方をそのまま覚えます。
ですので、暴言や悪口などはなるべく発しないようにしましょう。
反対に、感謝の言葉や褒める言葉を普段から使っていると、子供も周りに対し同じように接することができますので、ぜひ子供のお手本になってくださいね。
子供に判断させ、趣向を知る
子供のおもちゃや洋服、自由帳のデザインなどを親の趣味で決めていませんか?
近年ではSNSの影響で、写真映えするようにと親なんでも決めてしまう傾向にあるようです。
写真撮影も大切ですが、重要なのはカメラ越しではなく直接子供と目を合わせて会話することです。
なるべく早い段階で子供に好きな色や形を聞き選ばせておくと、彼らの趣向や性格を知るきっかけにもなります。
一人で子育てに悩んだら?(産後うつについて)

産後うつは病気だと知る
・子育てにやる気が起きない
・子供が憎い
・なぜ自分だけがつらいのだろう
このように感じてしまったときは、「産後うつ」という病気かもしれません。
病院でしっかりと治療(カウンセリング)ができる病気の一つですので、一人で抱え込まないようにしましょう。
自分ばかりを責めてしまうと、最悪の場合は育児放棄、そして離婚の原因にもなりかねません。
事前に旦那さんにもこのような病気があることを伝えておくと、一緒に治療をしたり家事のフォローをしてくれるようになります。
周りを頼る
両親や産婦人科の先生、友人などを積極的に頼りましょう。
なかなか会えない距離にいたとしても、電話で声を聞くことで気持ちが落ち着きます。
また、家事代行サービスも充実しているので進んで委託したり、身内に言えない悩みが出てきたら女性支援センターへ電話することもおすすめします。
旦那さんに「育児休業」を取得してもらう
一昔前は男性で育休を取る男性はなかなかいませんでした。
しかし、現代ではハードルが下がり、会社の規定に沿えば男性でも育休を取りやすくなりました。
もし育休が難しくても、有給を月に1度でも取得してもらうことで、母親の負担は大きく減ります。
終わりに

子供の教育に関して、不安な気持ちは和らいだでしょうか?
「出産・育児・家事」はどうしても女性一人の力でやり遂げなければ、というイメージが強かったように感じます。
しかし、実際はチームでするものです。
あなただけが頑張ったり背追い込む必要はありません。
今のうちに旦那さんと教育について話し合い、支え合いながら子育てを楽しんでくださいね。